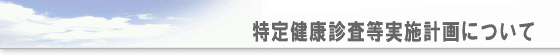| 背景及び趣旨 |
|
我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成して |
|
きた。しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面 |
|
しており、医療制度を持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。 |
|
このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険 |
|
者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定 |
|
健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導 |
|
(特定保健指導)を実施することとされた。 |
|
本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する |
|
基本的な事項特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関 |
|
する基本的事項について定めるものである。 |
|
なお、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年ごとに5年を一期として |
|
特定健康診査等実施計画を定めることとする。 |
|
|
| 当健康保険組合の現状 |
|
当健康保険組合は、日本精機(株)を母体として7事業所が加入している健康保険組 |
|
合である。被保険者及び被扶養者の約9割強が新潟県内に在住しており、県外営業所 |
|
(東京、大阪、埼玉他)および海外勤務者は全体の1割にも満たない。 |
|
当健康保険組合に加入している被保険者数は、平成18年度末現在3,401人で男性で |
|
男性が全体の7割強を占める。年間異動状況は加入数315人、脱退数204人、平均年齢 |
|
は38.8歳である。 |
|
定期健診については、各事業所単位で労働安全衛生法に基づき健康医学予防協会等 |
|
と実施し、生活習慣病等の人間ドックについては35歳以上の被保険者、被扶養配偶者 |
|
また、人間ドックの健診先は立川メディカルセンター・健康医学予防協会長岡健康管理 |
|
センター・上尾中央綜合病院と契約を取り交わし締結している。 |
|
平成19年度の人間ドック実施人数(予定)は255人を計画しており、今後は特定健診等 |
|
との関わりにより被扶養者を含め受診割合を高めて行く予定である。 |
|
|
| 特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 |
| 1. |
特定健康診査等の基本的考え方 |
|
日本内科学会等内科系8学会が合同でメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の |
|
疾患概念と診断基準を示した。 これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、 |
|
高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病 |
|
化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。 |
|
メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等 |
|
が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって |
|
生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。 |
|
|
| 2. |
特定健康診査等の実施に係る留意事項 |
|
今後、市町村国保の行う健康診査を受診している被扶養者の数を調査し、そのデータ |
|
を受領するとともに、今後は当健康保険組合が主体となって特定健診を行いそのデータ |
|
管理する。 |
|
任意継続被保険者についても同様である。 |
|
|
| 3. |
事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 |
|
被保険者については、事業主の実施した健診データを受領することにより特定健診を |
|
受診したこととし、受け取り方法は原則として電子媒体によることとする。 |
|
また、健診費用は事業主が負担するものとする。(特定健診より事業主健診が優先さ |
|
れる。) |
|
|
| 4. |
特定保健指導の基本的考え方 |
|
生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことであ |
|
る。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変 |
|
えることができるように支援することにある。 |
|
|
| Ⅰ 達成目標 |
|
1.特定健康診査の実施に係る目標 |
|
平成24年度における特定健康診査の実施率を78.6%とする。 |
|
この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標))を以下のように定める。 |
|
|
|
目標実施率 (%)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
国の参酌標準 |
| 被保険者 |
85.6 |
90.0 |
95.0 |
98.0 |
100.0 |
- |
| 被扶養者 |
5.0 |
7.5 |
14.1 |
24.5 |
33.1 |
- |
| 被保険者+被扶養者 |
61.5 |
65.0 |
70.0 |
74.9 |
78.6 |
80.0 |
|
|
|
|
2.特定保健指導の実施に係る目標 |
|
平成24年度における特定保健指導の実施率を45.0%とする。 |
|
この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標))を以下のように定める。 |
|
|
|
目標実施率(被保険者+被扶養者) (人)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
国の参酌標準 |
| 40歳以上対象者(人) |
2,237 |
2,314 |
2,398 |
2,486 |
2,582 |
- |
| 特定保健指導対象者数 (推計) |
604 |
626 |
649 |
674 |
701 |
- |
| 実施率(%) |
20.0 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
45.0 |
45.0% |
| 実施者数 |
121 |
157 |
195 |
270 |
315 |
- |
|
|
特定保健指導については、県外在住者にも配慮し、保健指導を行える機関に委託する。 |
|
|
|
3.特定健康診査等の実施の成果に係る目標 |
|
平成24年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び |
|
予備群の減少率を10%以上とする。 |
|
|
| Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 |
|
1.対象者数 |
|
(1)対象者数 |
|
被保険者 (人)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
| 対象者数(推計値) |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
| 40歳以上対象者 |
1,569 |
1,612 |
1,658 |
1,705 |
1,755 |
| 目標実施率(%) |
85.6 |
90.0 |
95.0 |
98.0 |
100.0 |
| 目標実施者数 |
1,343 |
1,451 |
1,575 |
1,671 |
1,755 |
|
|
|
|
被扶養者 (人)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
| 対象者数(推計値) |
668 |
702 |
740 |
781 |
827 |
| 40歳以上対象者 |
668 |
702 |
740 |
781 |
827 |
| 目標実施率(%) |
5.0 |
7.5 |
14.1 |
24.5 |
33.1 |
| 目標実施者数 |
33 |
53 |
104 |
191 |
274 |
|
|
|
|
被保険者+被扶養者 (人)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
| 対象者数(推計値) |
703 |
740 |
781 |
825 |
874 |
| 40歳以上対象者 |
2,237 |
2,314 |
2,398 |
2,486 |
2,582 |
| 目標実施率(%) |
61.5 |
65.0 |
70.0 |
74.9 |
78.6 |
| 目標実施者数 |
1,376 |
1,504 |
1,679 |
1,862 |
2,029 |
|
|
※対象者数とは事業主健診の受診者等を除外した保険者として実施すべき数 |
|
(被扶養者、任継被保険者、特別退職被保険者) |
|
※40歳以上対象者は保険者で実施せず他(事業主等)からデータを受領する数を加算 |
|
|
|
(2)特定保健指導の対象者数 |
|
被保険者+被扶養者
*40歳以上対象者とは特定健康診査の目標実施者数を表す (人)
| |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
| 40歳以上対象者) |
1,376 |
1,504 |
1,679 |
1,862 |
2,029 |
| 動機付け支援対象者 |
261 |
271 |
282 |
294 |
309 |
| 実施率(%) |
20.0 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
45.0 |
| 実施者数 |
52 |
68 |
85 |
118 |
139 |
| 積極的支援対象者 |
343 |
355 |
367 |
380 |
392 |
| 実施率(%) |
20.0 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
45.0 |
| 実施者数 |
69 |
89 |
110 |
152 |
176 |
| 保健指導対象者計 |
604 |
626 |
649 |
674 |
701 |
| 実施率(%) |
20.0 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
45.0 |
| 実施者数 |
121 |
157 |
195 |
270 |
315 |
|
|
|
| Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 |
|
1.実施場所 |
|
特定健診は、新潟県内在住の者については、事業主健診の委託先である新潟県 |
|
健康医学予防協会等または、人間ドック契約医療機関、各市町村国保が実施する |
|
健診事業スキーム等利用して行う。 |
|
県外在住者の特定健診については、健康医学予防協会が提携している健診機関 |
|
に委託する他、人間ドック契約医療機関に委託する。 |
|
特定保健指導は、新潟県内在住の者については、産業医のほか新潟県健康医学 |
|
予防協会、県内各市町村国保に委託して行う。 |
|
|
|
2.実施項目 |
|
実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)第2編第2章」に記載 |
|
されている健診項目とする。 (平成19年4月 厚生労働省 健康局 発行による) |
|
|
|
3.実施期間 |
|
実施期間は、通年とする。 |
|
|
|
4.委託の有無 |
|
(1)特定健診 |
|
被保険者・被扶養者が遠隔地等など 受診困難な場合は、代表医療保険者を |
|
通じて健診機関の全国組織との集合契約を締結し、代行機関として社会保険診療 |
|
報酬支払基金を利用して決済を行い、全国での受診が可能となるよう措置する。 |
|
(2)特定保健指導 |
|
被保険者・被扶養者が遠隔地等など 受診困難な場合は、「標準的な健診・保健 |
|
指導プログラム第3編6章」の考え方に基づきアウトソーシングする。 |
|
また、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い、全国で |
|
の利用が可能となるよう措置する。 |
|
|
|
5.受診方法 |
|
遠隔地の場合は、当健康保険組合が、被保険者・被扶養者のうち特定健診等対象 |
|
者の分の受診券・利用券を事業主を通じて対象者に送付する。 |
|
当該被保険者・被扶養者は、受診券又は利用券を健診機関等に被保険者証ととも |
|
に提出して特定健診を受診し、特定保健指導を受ける。 |
|
受診の窓口負担は無料とする。 ただし、規定の実施項目以外を受診した場合は |
|
その費用は個人負担とする。 |
|
|
|
6.周知・案内方法 |
|
周知は、当健康保険組合「健保だより」やホームページに掲載して行う。 |
|
|
|
7.健診データの受領方法 |
|
健診のデータは、契約健診機関から代行機関を通じて電子データを随時 (又は月 |
|
単位) 受領して、当健康保険組合で保管する。 また、特定保健指導について外部 |
|
委託先機関実施分についても同様に電子データで受領するものとする。なお、保管 |
|
年数は5年とする。 |
|
|
|
8.特定保健指導対象者の選出の方法 |
|
特定保健指導の対象者については、数量の面から長岡市、小千谷市、見附市、 |
|
その他県内に在住する者から優先して選出する。 また、効果の面からは、40歳代の |
|
者から優先して選出する。 |
|
|
| Ⅳ 個人情報の保護 |
|
当健康保険組合は、日本精機健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。 |
|
当健康保険組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報 |
|
を外部に漏らしてはならない。 |
|
当健康保険組合のデータ管理者は、常務理事とする。また、データの利用者は当健 |
|
康保険組合の職員に限る。 |
|
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。 |
|
|
| Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 |
|
本計画の周知は、各事業所にパンフレットを送付するとともに、「健保だより」及び |
|
ホームページに掲載する。 |
|
|
| Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し |
|
当計画については、毎年健康管理推進委員会において見直しを検討する。 |
|
また、平成22年度に3年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合その他必要 |
|
がある場合には見直すこととする。 |
|
|
| Ⅶ その他 |
|
計画書がまとまり次第、改めて各事業主に対しての特定健康診査等の必要性を説 |
|
明し、連携の協力をお願いし、今後、事業主側で保健師を採用した場合は、特定健診 |
|
・特定保健指導の実践養成のための研修に随時参加させる。 |
|
また、今後は、年間スケジュールを作成し、被保険者・被扶養者の受診率アップを |
|
目指し広報活動の方法を検討してゆくものとする。 |